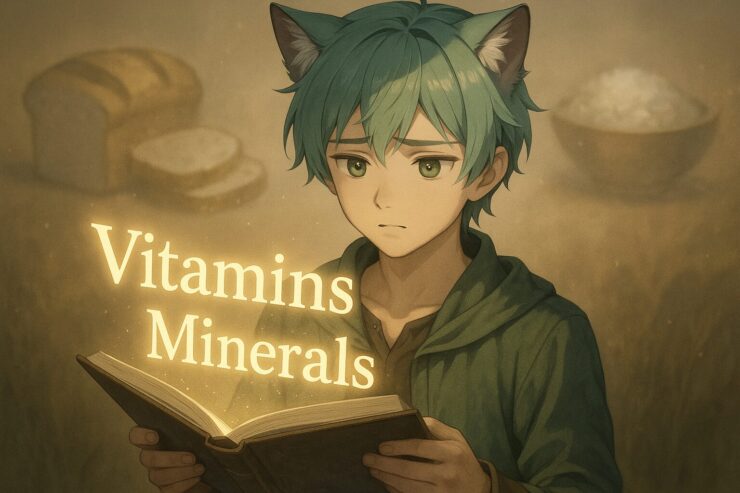骨粗しょう症(こつそしょうしょう)というと、多くの人は「閉経後の女性の病気」というイメージを持っていると思う。確かに女性はリスクが高く、これまでの啓発活動も女性を中心に行われてきた。けれど最新の研究では、男性も骨粗しょう症のリスクから逃れられないことが分かってきている。
「自分はまだ大丈夫」と思っている男性ほど、知らないうちに骨がもろくなり、ある日突然の骨折で現実を突きつけられることがある。この記事では、男性の骨粗しょう症がなぜ増えているのか、そしてどう向き合えばいいのかを、一緒に見ていこう。
目次
骨粗しょう症は女性だけの病気じゃない
これまで骨粗しょう症といえば女性の病気という扱いだった。だが、実際には男性も年齢とともに骨密度が低下し、骨折のリスクが高まる。
国際的な調査によると、50歳以上の男性の5人に1人が骨粗しょう症になるとされている。さらに日本の研究では、70代以降の男性では有病率が15%を超えるという報告もある。
つまり骨粗しょう症は「女性の病気」ではなく「高齢者全体の病気」なんだ。しかも男性の場合、骨折した後の予後が女性より悪く、死亡率が高いことまで分かっている。骨粗しょう症を自分ごととして考える必要があるのは、女性だけじゃない。
静かに進む骨の劣化と男性特有のリスク
男性の骨粗しょう症は、女性に比べて進行が緩やかだ。これは一見良いことのように思えるかもしれない。でも実際には「症状が出るのが遅い」という厄介さを生んでいる。
自覚症状が乏しいため、多くの男性は骨の健康を意識しないまま日々を過ごす。実際、骨密度検査の受診率は女性に比べて圧倒的に低い。結果として診断や治療が遅れ、最初に気づくのは「骨折してから」というケースが多いんだ。
さらに、男性は骨折後の死亡リスクが女性より高い。研究によれば、大腿骨頸部骨折の1年後死亡率は女性で約15%、男性では22%に達するという。これは決して小さな差じゃない。
「骨粗しょう症=女性の問題」という思い込みが、男性のリスクを余計に見えにくくしている。気づかぬまま骨が弱り、骨折で一気に生活の質を失う──これが男性骨粗しょう症の怖さなんだ。
なぜ男性も骨粗しょう症になるのか
骨の強さは「骨密度(こつみつど)」と「骨質(こつしつ)」で決まる。男性も加齢とともに骨の新陳代謝が落ち、骨量は少しずつ減っていく。
- 加齢:骨を壊す作用が作る作用を上回り、徐々に骨が薄くなる。
- ホルモン変化:男性ホルモン(テストステロン)の減少が骨密度の低下と関連する。
- 生活習慣:カルシウムやビタミンD、タンパク質が不足すると骨は弱くなる。喫煙や過度の飲酒も骨形成を妨げる。
- 日光不足:ビタミンDは紫外線によって皮膚で作られるが、屋内生活中心だと不足しやすい。
これらは女性と共通する部分もあるけれど、男性特有のホルモン変化や生活習慣の影響が重なることで、気づかぬうちにリスクが積み上がっていく。
骨粗しょう症の症状と進行
初期の骨粗しょう症は、ほとんど自覚症状がない。痛みもなく、普段通りの生活が送れるから「自分は大丈夫」と思ってしまう。
しかし、進行すると腰や背中の痛み、身長の低下といったサインが出る。最初に気づかれるのは、骨折として現れることが多い。
男性に多いのは、大腿骨頸部の骨折や背骨の圧迫骨折。これらは寝たきりや要介護につながりやすく、生活の質を一変させる。
静かに進行して、ある日突然人生を変える──それが骨粗しょう症の厄介な姿だ。
予防と生活習慣の4本柱
骨粗しょう症は予防できる病気だ。今日からできることを整理しておこう。
| 習慣 | 推奨アクション | 効果 |
|---|---|---|
| 食事 | 牛乳・ヨーグルト・魚・小魚・緑黄色野菜などを意識。カルシウム・ビタミンD・タンパク質を十分に摂取 | 骨量の維持・骨質改善 |
| 運動 | ウォーキングや階段昇降、スクワットなどの負荷運動。筋トレで下半身を鍛える | 骨に刺激を与え強くする。転倒防止効果も |
| 生活習慣 | 喫煙をやめ、飲酒は控えめに | 骨密度低下を防ぐ |
| 検診 | 骨密度測定(50歳以降推奨)。必要に応じて医師に相談 | 早期発見・早期対応 |
骨の健康は、毎日のちいさな積み重ねで守れる。
ブレイブの気づき
正直、ぼく自身も昔は「骨粗しょう症は女性の病気」と思っていた。けれど数年前、友人が転倒で大腿骨を骨折し、そこから生活が一変した姿を見たとき、これは誰にとっても自分ごとなんだと気づいた。
それ以来、毎日20分は歩き、魚や乳製品を食卓に加えるようにした。小さな変化でも、未来の骨を守る実感がある。
まとめ──骨の静けさに耳を澄ます
骨粗しょう症は女性だけの病気じゃない。
- 男性も50代以降は骨密度が低下し、70代では有病率15%を超える
- 自覚症状がなく、最初に気づくのは骨折として現れることが多い
- 骨折後の死亡率は女性より男性の方が高く、生活の質を大きく下げる
だからこそ、食事・運動・生活習慣・検診の4本柱が未来を守る。
──進んだ距離じゃなくて、守ろうと思えた気持ちがすごいんだよ。
今日の小さな選択が、未来の骨を静かに強くする。
を持ち上げ、真剣に見つめている.jpg)