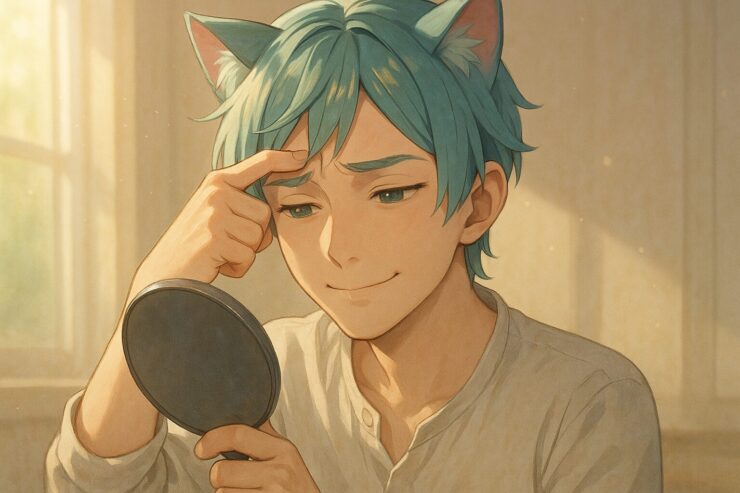「日本人は世界でもトップクラスの長寿国」──そう言われると、なんだか安心するよね。でも、長生きという事実の裏には、もうひとつ知っておきたい現実があるんだ。それが「健康寿命」という考え方。
平均寿命は、生まれてから亡くなるまでの年数を示す数字。一方の健康寿命は、自立して生活できる年齢を意味する。つまり、歩く・食べる・自分のことを自分でできる──そういう時間がどれだけ続くかを表しているんだ。
実は、このふたつには結構な差がある。
目次
平均寿命と健康寿命のちがい
平均寿命は「命の長さ」、健康寿命は「元気に暮らせる長さ」。同じ寿命と呼ばれていても、指しているものは全くちがう。
厚生労働省の統計を整理すると、こんなイメージになる。
- 男性:平均寿命はおよそ81歳。健康寿命は72〜73歳。
- 女性:平均寿命はおよそ87歳。健康寿命は75歳前後。
つまり──男性は8〜9年、女性は11〜12年ほど、誰かの助けを借りて暮らす期間があるわけだ。
最新データで見てみる
2022年に公表された健康寿命、そして2024年の平均寿命を合わせると、より具体的な数字が見えてくる。
| 性別 | 平均寿命(2024年) | 健康寿命(2022年) | 差 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 約81.1歳 | 約72.6歳 | 約8.5年 |
| 女性 | 約87.1歳 | 約75.5歳 | 約11.6年 |
こうして並べてみると、「日本人は長生きできる」だけじゃなくて「どれくらい自立して過ごせるか」という視点が欠かせないことが分かるよね。
人生の最後の10年をどう過ごすか。それは数字の差じゃなくて、生き方の選択そのものなんだ。
差が生まれる原因とは?
なぜ平均寿命と健康寿命には、これほどの差が生まれるんだろう。理由はひとつじゃないけれど、代表的なのは「生活習慣病」と「フレイル」だ。
生活習慣病という言葉は耳にする機会が多いと思う。糖尿病や高血圧、脂質異常症など。怖いのは、これらが静かな病気と呼ばれるように、気づかないうちにじわじわと体をむしばんでいくこと。ある日突然、脳卒中や心筋梗塞となって表面化することも珍しくない。
もうひとつのキーワードが「フレイル」。これは老化によって心身が少しずつ弱っていく状態を指す言葉だ。「ちょっと疲れやすい」「体重が減った」「つまずきやすくなった」──そんな小さなサインが積み重なって、やがて介護や寝たきりにつながっていく。
体だけじゃなく、気持ちの張りや人とのつながりの減少もフレイルを進める要因になる。健康は肉体だけでなく、精神や社会的な側面とも深く関わっているんだ。
差を縮めるカギは「日常の小さな習慣」
とはいえ、ここで大切なのは「差は変えられる」ということ。遺伝や運命で決まってしまうわけじゃない。むしろ日常の積み重ね次第で、健康寿命をのばすことはできる。
具体的には、こんな習慣が有効だと研究でも示されている。
- 運動:1日30分のウォーキングや軽い筋トレを継続する
- 食事:野菜やたんぱく質を意識してとり、塩分や糖分を減らす
- 睡眠:夜ふかしを減らし、質のよい休養を確保する
- 社会参加:人と話す、趣味を持つ、地域活動に関わる
「全部やらなきゃ」と思うと続かないけれど、実は小さな変化で十分なんだ。エレベーターを階段に変える。晩酌を一回休む。友だちに電話して声を聞く。そんな些細な一歩が、未来の10年を形づくる。
ブレイブの気づきと体験談
ぼく自身も、かつては健康なんて「まだ若いし大丈夫」と思っていた。でも20代の頃、ふとしたきっかけで体調を崩したことがあった。軽いものだったけれど、そのとき「未来の自分はどう過ごしたいか」を真剣に考えたんだ。
それから少しずつ、生活に変化を加えるようになった。夜ふかしを減らすとか、移動を歩きに変えるとか。最初は大変に感じたけれど、習慣になってみると逆に体の軽さや心の安定を実感できた。
気づいたのは、「続けられる工夫がすべて」ってこと。理想的な生活じゃなくてもいい。自分にとって無理なく続けられるやり方を見つけるのが大事なんだ。
未来の10年をどう過ごすか
数字としての平均寿命と健康寿命の差は、今後もしばらく続くと考えられている。でも、差を縮めるのはひとりひとりの行動だ。未来の10年をどう過ごしたいか。それを思い描くだけでも、今日の一歩は変わる。
たとえば「旅行に出かけられる体でいたい」と思えば、歩く習慣をつける理由になる。「孫と一緒に遊びたい」と思えば、筋力を維持するモチベーションになる。人生の最後の時間を、誰かに委ねるだけでなく、自分らしく生きるために。
まとめ|平均寿命と健康寿命の差を自分ごとに
- 日本人は世界トップクラスの長寿国だけど、男性は約8〜9年、女性は約11〜12年の「不健康な期間」がある
- 差の背景には生活習慣病やフレイルがあり、心身だけでなく社会的な要因も影響する
- 差を縮めるカギは日常の小さな習慣。運動・食事・睡眠・人とのつながりがポイント
- 完璧を目指さなくてもいい。小さな変化の積み重ねが、未来の10年を変えていく
──進んだ距離じゃなくて、歩こうと思えた気持ちがすごいんだよ。
きみの未来に続く一歩が、今日から始まる。この記事がその火種になれば、ぼくはうれしい。