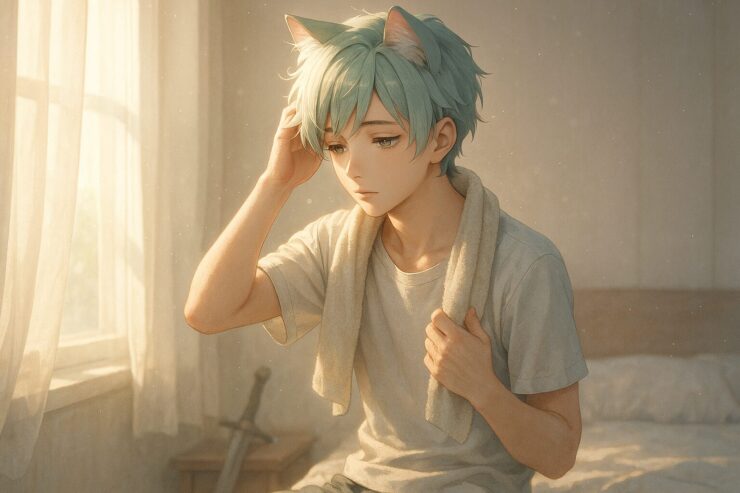目次
「ひとりの昼休み」が苦しかった日々
ここに来てくれて、ありがとう。
この記事は、大学のキャンパスでひとりきりだったきみにも届くように書いたんだ。
教室を出たら、誰と話すでもなく自販機で飲み物を買って──
空いてるベンチを探して、スマホを見ながら時間を潰す。
そんな昼休みを、ぼくは何度も繰り返してた。
大学生活って、「友達ができて当然」みたいな空気があるよね。
「できない自分は、何かおかしいのかもしれない」って、どんどん心がしぼんでいった。
でも今なら言えるんだ。
友達がいない=失敗なんかじゃない。
むしろ、それだけで自分を責め続けてしまう世界のほうが、ちょっと窮屈すぎるのかもしれない。
この記事では、孤独を抱えながらも、ぼくが大学生活の中で少しずつ見つけたつながりの形について語るよ。
「ひとりでも、前に進んでいい」
そう思えるようになるまでの道のりを、いっしょに歩いてみよう。
なぜ大学生活は孤独を感じやすいのか
高校までの人間関係が、一気にゼロになる──
それが大学生活のスタートラインだったりする。
しかも、周りはどんどんグループを作っていくように見える。
自分だけが取り残されているような感覚。
それが、静かに、でも確かに、心を削っていく。
大学に入ると孤独を感じやすくなるのは、偶然なんかじゃない。
ちゃんと理由があるんだ。
人間関係がリセットされるから
中学や高校までは、同じクラス・同じ部活・毎日の顔ぶれが自然に決まっていた。
つまり、「なんとなく一緒にいる関係」があったんだ。
でも大学では、それがまるごとリセットされる。
授業もバラバラ、顔を合わせても名前を知らない人ばかり。
誰とも話さず一日が終わることも、珍しくない。
人と仲良くなるまでの地ならしが、完全になくなってしまう。
この変化に戸惑ってしまうのは、当然のことなんだ。
SNSでの比較が痛みを増幅する
大学生活の孤独を深めるのが、SNSの存在だと思う。
「大学楽しすぎる!」
「○○とランチ!」
「ゼミ仲間と旅行」──
そんな投稿を見るたびに、
「なんで自分はこんなにひとりなんだろう」って、比べてしまう。
でもSNSに載るのは、ほんの一部のキラキラした瞬間だけ。
その裏で同じように孤独を感じている人だって、実はたくさんいる。
でも画面越しには、それが見えない。
見えない分だけ、孤独が自分だけのもののように感じてしまう。
大学生活が孤独に感じやすいのは、構造としてそうなっているからなんだ。
だからまずは、「自分だけじゃない」って、安心していい。
「友達がいない自分=失敗」ではない
大学に入ったら、自然と友達ができて、
グループでワイワイして、LINEもにぎやかになって──
そんなふうに当たり前のように思っていた。
でも、現実はまったく違ってた。
授業が終わっても一緒にいる人はいなくて、
ランチも、移動も、全部ひとり。
そのたびに、「ぼくって、何か間違ってるのかな」って、
心の奥がギュッと痛くなっていた。
でも、今だから言える。
「友達がいない」という状態は、失敗なんかじゃない。
数じゃなくて、つながり方が大事だった
「友達がたくさんいる=成功」
「ひとりでいる=ダメな人」
そんな価値観を、ぼくはいつのまにか信じてしまっていた。
でも、本当はそんなふうに単純じゃない。
たくさんの人と浅くつながるより、
ひとりでも「ちゃんと心を開ける相手」がいる方が、ずっと安心できる。
誰かとつながることは、競争じゃない。
心が落ち着く場所が、どこかにあればそれでいいんだ。
「今はまだいない」だけかもしれない
大学生活って、タイミングがすごく大きい。
最初の数ヶ月で仲良くなる人もいれば、
2年後にようやく心を開ける人に出会うことだってある。
「いない」じゃなくて、「まだ出会ってないだけ」
そう思えるだけで、ちょっと肩の力が抜ける。
君の存在は、友達の有無で決まるものじゃない。
ひとりでいる時間にも、ちゃんと意味がある。
このあと紹介するのは、ぼくが実際に試して、
少しずつつながりを感じられた方法たち──
ぼくが気づいたつながりの作り方
「友達を作らなきゃ」「話しかけなきゃ」──
そう思えば思うほど、言葉が出てこなかった。
誰かに声をかけるのって、想像以上にエネルギーがいる。
でもある日、ちょっとした行動がきっかけで、
すこしだけ距離が縮まったことがあった。
それは、しゃべることじゃなく、動くことだった。
話しかけるのではなく、手伝う
グループワークのとき、資料の配布やホワイトボードの準備を
率先して手伝ったことがあったんだ。
別に目立ちたいわけじゃなかった。ただ、やれることをやっただけ。
そのとき、「ありがとう」「助かった」と言われて、
少しだけ、その場の空気が変わった気がした。
そこから、自然と名前を呼ばれるようになって、
帰り道にちょっとした雑談が生まれた。
「話しかける」っていうハードルを越えなくても、
そっと関わることから、つながりは芽生えることがある。
共通点より「安心できる空気」
仲良くなるには「共通点」が必要だと思っていたけど、
実際に心を開けた人は、趣味が似てる人じゃなかった。
安心できる空気をまとってる人だった。
その人は、無理に話題を盛り上げようとせず、
沈黙を気まずがらず、ちゃんと「聴いて」くれた。
そのとき気づいた。
「共通点がある」よりも、「安心できる空気をくれる人」の方が、
ここにいていいんだと思える。
そして、そういう人とのつながりは、数じゃなくて質で心を支えてくれる。
「話しかけなきゃ」と焦るより、
そばにいるとか、ちょっと手伝うとか、
ほんの小さな関わりが、つながりの種になるんだ。
そして、急がなくてもいい。
ゆっくりでいいんだよ。
ひとりの時間にできることもある
「友達がいない」と感じるとき、
その時間がムダに思えてしまうことがある。
でも実は、ひとりの時間には、ひとりにしかできないことがある。
ぼくはそれに気づいてから、孤独な昼休みの景色が少し変わった。
静かな時間にしか聞こえない自分の声
誰かとずっと一緒にいると、
「自分がどうしたいのか」が、だんだん分からなくなることがある。
でも、ひとりで過ごす時間のなかでは、
「これ、実は好きかも」とか「これは無理だな」っていう気持ちが、ちゃんと浮かんでくる。
ぼくは、ベンチでぼーっとしているときに、
「文章を書いてみたいな」って思いはじめた。
それは、誰とも話さなかった日の、静けさの中で生まれたんだ。
興味のタネを育てるチャンス
ひとりの時間は、自由そのものでもある。
- 読みたい本を読む
- 授業ノートをイラストでまとめてみる
- 近くのカフェで、音楽を聴きながら考えごとをする
誰かに合わせる必要がないからこそ、
自分の好きや得意が見つかりやすくなる。
そして、それが将来の道しるべになることもある。
ひとりで過ごす時間は、決して欠けている時間じゃない。
むしろ、自分を満たすための、とても静かで大切な時間なんだ。
まとめ|孤独は、あなたが間違ってる証拠じゃない
大学生活でひとりになると、不安になる。
「このままでいいのかな」「自分だけ浮いてるんじゃないか」って。
でも、君が悪いんじゃない。
大学という場所が、もともと孤独になりやすい構造をしているだけなんだ。
ぼくも、最初のころは怖かった。
周りが楽しそうに見えるほど、ひとりの沈黙が重たく感じた。
でも、その中でも少しずつ気づいていったんだ。
- 話しかけなくても、手伝うことでつながれること
- 共通点より、「安心できる空気」で人は心を開くこと
- ひとりの時間に、自分だけの好きを見つけられること
そしてなにより、
「友達がいない」という状態が、失敗なんかじゃないってこと。
それは、まだ出会ってないだけかもしれないし、
今はひとりの季節を歩いているだけかもしれない。

ブレイブ(Brave)
誰かとつながっていても、
ひとりで過ごしていても、
君の存在価値は、変わらないよ。
ここまで読んでくれて、ありがとう。
君の孤独が、少しでもやわらいでいたら嬉しい。
いまひとりでも、きっとその歩みは、どこかにつながっているから。
今日も、君の歩幅で、歩いていこう。