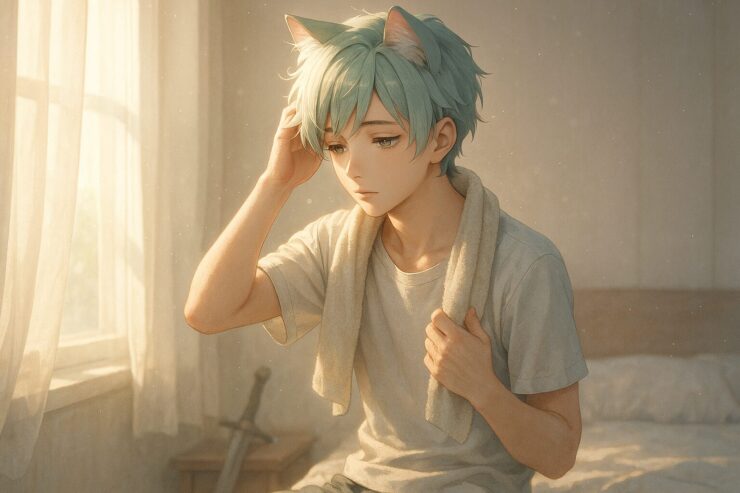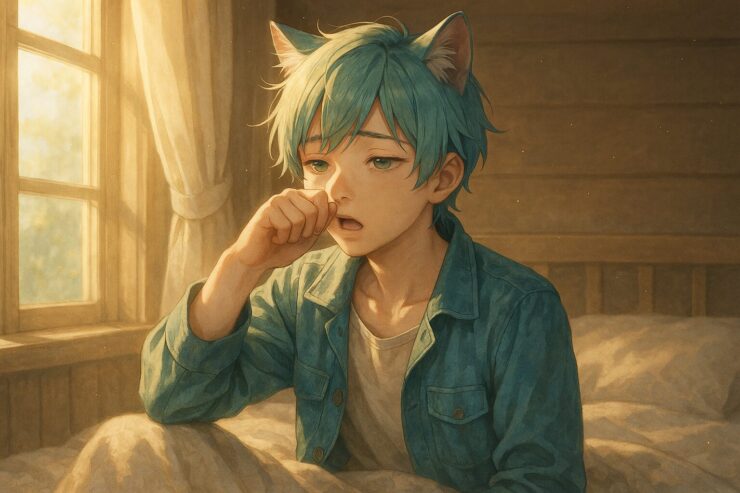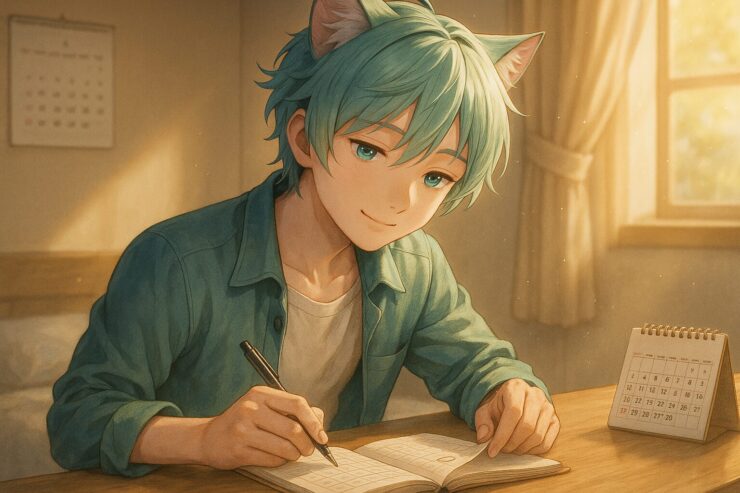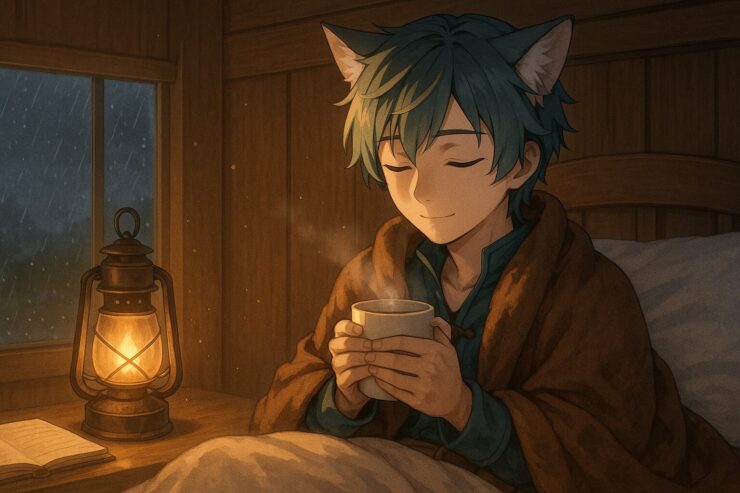「明日こそ早起きするぞ」って決めたのに、
結局また寝坊して自己嫌悪──。
そんな日を、何度繰り返したか分からない。
ぼくにも、同じだった時期があるよ。
だから、きみにまず伝えたいのは──
「きみがダメなんじゃない」ってこと。
意思が弱いわけでも、根性が足りないわけでもない。
ただ、起きれない仕組みの中で、がんばろうとしてただけなんだ。
朝起きるって、意外と「メンタル」より「設計」なんだよね。
だから今回は、気合や努力ではなく、起きたくなる設計図をいっしょに描いていこう。
それは、きっとやさしい朝への第一歩になるから。
目次
起きれないには理由がある
🔸脳は「朝が怖い」と感じていることもある
「朝起きるのがつらい」
「布団の中で、しばらく動けない」
それってただの眠気だけじゃないこともあるんだ。
もしかすると、脳が「朝=ストレス」と覚えてしまっているのかもしれない。
たとえば、
- ・朝起きたらすぐに仕事のプレッシャーが待っている
- ・SNSを見ると、他人の充実した朝活に落ち込む
- ・急かされるように準備して、心が置いてけぼりになる
そんな体験が重なると、脳は「朝がしんどい時間」として記憶してしまうんだ。
だから、目覚ましが鳴っても起きたくない。
布団の中が一番安心できる場所に感じてしまう。
これはサボりなんかじゃなくて、ちゃんとした防衛反応なんだよ。
🔸気合じゃなく、条件で起きる力を引き出す
「よし、明日こそ起きるぞ!」
そんな気合いだけで毎朝戦っていた時期が、ぼくにもあった。
でも、気合ってすぐに切れる。
体は眠くて、心も重くて、すぐ負けてしまう。
だから気づいたんだ。
気合ではなく、条件で起きる力を引き出すことのほうが、ずっとやさしいって。
たとえば、
- 起きたらすぐ光が入るようにカーテンを少し開けておく
- 布団のそばに、好きな香りのオイルやハンドクリームを置いておく
- 朝一番で楽しみにしてる飲み物や音楽をセットしておく
それだけでも、「起きる=つらい」を、「起きる=ちょっといいことある」に変えていける。
起きたくなる朝をつくることは、自分を責めずに始められるやさしい改革なんだ。
朝起きるために、夜から始める設計術
🔸就寝30分前の行動がすべてを決める
早起きを成功させるカギは、実は「朝」じゃなくて「夜」にある。
とくに大事なのが、寝る前30分の過ごし方なんだ。
ぼく自身、「何時に寝てもいいから、ちゃんと朝起きたい」って思ってた時期があったけど、
やっぱり夜の質が朝にそのまま反映される。
とくに寝る前の行動は、脳の状態に直結していて──
- 寝る直前までスマホを見ていると、脳はまだ昼モードのまま
- 予定や不安を考えながら寝ようとすると、眠りが浅くなる
- 急に布団に入っても、身体がまだ起きてていいと判断してしまう
だからこそ、「夜の30分」を静かにしていくことが、
次の日のやさしい目覚めにつながっていく。
この30分間は、いわば「明日の自分への贈り物」なんだ。
🔸「照明・音・画面」を整えるだけでOK
難しいことをしなくてもいい。
まずは3つの環境要素を整えるだけで、睡眠の質が大きく変わってくる。
① 照明:
部屋の明かりをオレンジ系のやさしい光に変える。
できれば、間接照明やデスクライトだけで過ごしてみよう。
→ 脳が「もうすぐ眠る時間だ」と自然に認識する。
② 音:
好きな落ち着く音楽(ピアノ、雨音、環境音など)を小さめに流す。
できれば歌詞なしがベスト。
→ 呼吸が深くなり、副交感神経が優位に切り替わる。
③ 画面:
スマホやPCから離れる。少なくとも30分前にはOFF。
→ ブルーライトから脳を守って、眠気を促す。
この3つを少し意識するだけで、
「眠れなかった夜」が「整えられた夜」に変わっていく。
そうすると、次の日の朝がちょっとやわらかくなるんだよ。
起きたくなる朝をデザインする
🔸起きた瞬間、最初に触れるのは「光」と「香り」
「朝起きたくない」と思うのは、
単に眠いからというより、起きたあとに楽しみや安心感がないからかもしれない。
だから、まずは「起きてすぐに触れるもの」を、
ちょっとだけ好きなものに変えてみよう。
たとえば──
- カーテンを少しだけ開けておいて、朝の自然光を最初に浴びる
- 枕元にアロマスプレーやお気に入りの香りのハンドクリームを置いておく
- やわらかいブランケットや、肌ざわりの良いタオルを使ってみる
人の感覚って、「触れる・見る・香る」で一気に変わる。
そして、その最初の感覚が、その日の気分を左右するんだ。
つまり、「朝をやさしく始める環境」は、自分でデザインできるということ。
🔸朝の楽しみを前日にセットする(飲み物・音楽・推しアイテム)
もうひとつ、大切な工夫がある。
それは「明日の朝がちょっと楽しみになる仕込み」を前の日のうちにしておくこと。
ぼくの場合は──
- 朝だけ飲む「ちょっと特別なドリップコーヒー」を用意しておく
- お気に入りの目覚め音楽をプレイリストにしてセット
- 見るだけで嬉しくなるグッズや小物を、朝の視界に置いておく(ぬいぐるみ・推しの写真など)
そうやって、朝に会いたくなる楽しみを、そっと置いておく。
「起きなきゃ」じゃなくて、
「ちょっと楽しみな朝が待ってる」って思えたら、目覚ましの音も少し優しく聴こえてくる。
朝を我慢の時間から、やさしい再会の時間に変える。
そんな工夫を、少しずつ加えていこう。
ぼくが実践した「早起きリハビリ」のステップ
🔸まずは平日だけでもいい
早起きって、「毎日やらなきゃ」「習慣にしなきゃ」と思うほど、苦しくなる。
だからぼくは、まず週5じゃなくて週3くらいを目指すようにした。
「月曜・水曜・金曜だけは、30分早く起きてみる」みたいにね。
それでもできなかった日は、
「きょうは、そういう日だったんだ」と思うようにしてる。
完璧じゃなくていい。
平日だけ/1日おき/週末だけでも、立派なリズムになる。
むしろ、続かないことを責めるより、
できた日を見つけて自分をねぎらう方が、よっぽど大事なんだ。
🔸「できた日」を書き残すだけで、脳は変わる
早起きに限らずだけど、「できた記録」って、じつはすごく効果があるんだ。
ぼくは、ノートの端に「◎ 起きれた」「△ ちょっと遅れた」「× 寝坊!」って書くようにしてる。
この記録があると、
「今週は2勝3敗だったな」みたいに振り返れるし、
◎が並んだ週を見ると、ちゃんと自分を誇らしく思える。
大事なのは、完璧を求めることじゃなくて、
「今日もトライできた」って記録してあげること。
その記録が、脳の中で起きるのが当たり前というスイッチを、ゆっくり育ててくれる。
自分との信頼関係を、朝の時間から築いていこう。
まとめ|「起きれなかった日」にも意味がある
きみにとって、「朝」はどんな時間だろう?
ぼくにとって朝は、かつてちょっと苦手で、少し怖くて、でも──変わっていった時間だった。
起きれない自分を責めるよりも、
起きれた自分を誇るよりも、
「起きようと思えた気持ち」こそが、一番やさしくて尊い一歩なんだと思う。
朝が苦手なきみへ。
夜にくたびれたきみへ。
それでもまた「起きてみようかな」と思えた、今のきみへ。
朝に向かうことは、自分と和解することでもある。
やさしい光を迎える準備は、きっと今からでも、少しずつできるよ。

ブレイブ(Brave)
「起きれたかどうかじゃなくて、起きようと思えたことが、もうすごいんだよ」